
自由の彼方で (講談社文芸文庫)
著者の半自伝的小説である。とはいえ徒に回顧的なのではなく、著者は主人公の少年を「僕の滑稽な死体」と呼んで客体視し、冷静な文体で物語を進めており好感がもてる。少年は家出の後コックとして働きながら悲惨な環境に耐えていくうちに、自らの血=死を盾に闘うという方法を身につけてゆく。その後、車掌となって盲目的に非合法運動に猛進してゆくが、いとも簡単に検挙され抜け殻同然の姿で生きることを余儀なくされる。少年は常に滑稽なほど単純無知でありその悲劇性すら思い込みに過ぎないのだが、それだけに、その懸命な姿は壮絶である。救いを求めて「ツァラトゥストラ」を読むものの何の答えを見出せず茫然となるラストシーンは特に印象的。観念小説だが決して難解ではなく、ごく自然に「実存」という言葉を感じさせる。
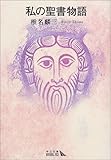
私の聖書物語 (中公文庫BIBLIO)
著者の椎名氏は元共産党員で、戦前は獄中にありましたが、共産主義を捨てるという転向により釈放され、後にキリスト教徒となりました。本書は椎名氏のキリスト教をめぐる信仰告白ともいえるべき書です。世間一般のイメージでは、キリスト教徒とは、全能なる神を信じ、イエス・キリストの奇蹟を信じている者かもしれません。しかしながら、椎名氏はそこに疑問を投げかけます。むしろ、奇蹟を信じられない点こそ、キリスト教にとって大切なことだと説きます。信じられなければそれで良いではないか、その姿こそまごうことのない厳然とした人間の事実であり、キリストは苦しみや悩みなどで人間性を奪われて貧弱に生きている私たちのために、人間性をとりかえそうとやってこられた方なのだからと椎名氏は言います。マリアの処女受胎、イエスの復活など様々な奇蹟を信じられずキリスト者はつまずくことがあるでしょう。けれども、本書を読むと、お仕着せの綺麗な服を着ているような、まったくつまずかない品行方正なキリスト教徒の方がむしろ何かおかしいように感じられるのです。椎名氏によれば、奇蹟は信じられないものであるということも、また信じられるものであるということも、キリストの前では同じことで生かされている一人の人間である証拠です。信じることと信じないことの葛藤を繰り返す、ここに椎名氏のユニークな思索の過程が見られます。聖書入門と言うよりも、むしろ一人のキリスト者の独白と言えるでしょう。

煙突の見える場所 [DVD]
1953年公開、五所平之助監督の映画。この年は邦画の全盛期にして当たり年だったようで、キネマ旬報ベストテンでは、「にごりえ」(今井正)が一位、「東京物語」が二位、「雨月物語」が三位。この「煙突の見える場所が四位だった。
1950年代前半の日本の、東京に暮らす庶民の生活ぶりがリアルに描かれているのが興味深い。この頃はまだ終戦後の混乱した時代を引きずっているようで、まだまだ人々の生活も貧しい。バラックのような二階建、質素(というより粗末)な庶民の住宅の様子、まだ木造が多い商店街、舗装されていないバス道など興味深い。
登場人物も、世相を踏まえてリアルに描かれる。東京の下町に住む会社員の隆吉(上原謙)と再婚した戦争未亡人の弘子(田中絹代)。弘子は未だに戦争の影をひきずり、健気だがどこか影がある。平穏に見えていた夫婦の生活も、弘子のアルバイトをきっかけに不信感が芽生え始まる。また、下宿人二人(仙子と健三)も互いに好意を持っているが、今一つ仲が進展しない。このあたりの描写は実にリアルで、当時の日本の世相と人々の考え方を知る上で貴重だと思う。
弘子の亡くなったと思われていた前夫(塚原)が赤ん坊を置き去ったことから、夫婦・下宿人のそれぞれの微妙な違いが際立ち緊張が高まる。自分にはまったく関係のない赤ん坊にいら立ち、弘子の家出にも優柔不断で行動力に欠ける隆吉。我儘な部分が多々あり、戦前からの封建的な部分をひきずっていることがわかる。
下宿人二人も、現実的で行動的な仙子と観念先行型の健三の感覚の違いが露わになっていく。この二人にも「すれ違い」の部分があったことがわかる。
一方で新たな展開も生じる。実の親を探す健三、徐々に愛情を示し始める隆吉。ばらばらになりかけた夫婦、そして下宿人を含めて徐々に結びついていく。赤ん坊は登場人物のちぐはぐで問題をかかえる部分を明示し混乱させるとともに、それを踏まえた上での新しい生き方を示すキーとして描かれる。
様々な場所で、煙突の数が変わって見える。それぞれの生活、人生の在り方を象徴するかのように。ラストの健三と仙子の場面で、煙突の距離が近づき、ほとんど重なって見えるシーンは、二人が互いを理解し近づいていたようにも思える。また、同じ人間であっても気の持ち方一つで、(お化け煙突のように)まったく違って見えるということだろう。
原作は椎名麟三だが、人の考え方・生き方は様々だし、世相によって左右される。しかし、お互い相手を理解することは可能であるし、またそうやって生きていかなければならないというメッセージのように思えた。
この映画の素晴らしいところは、社会と人物の描写に高度なリアルさを追求しながら、その中でどう生きていくか、人とかかわるかということを、煙突をメタファーにして表現しているところだと思う。
今の時代から見ると、人物の描き方やストーリーの展開に若干違和感があるかも知れないが、1950年代前半の生活や人々の考え方を理解する上では貴重な映画だし、それを踏まえた上で観れば見ごたえのある映画だと思う。







