
Interview
ジェントル・ジャイアントの7作めで「スリー・フレンズ」と並びヘビーな一枚。ライブをはさんで次作「ミッシング・ピース」では変則リズムも、へんてこな作曲もやらなくなってしまったので、いわゆるプログレッシブな作品としては、この一枚が最後の制作です。
とにかくGGの全作の中でも、最も複雑な曲構成を誇っていて、アレンジも破壊的というか一度聞いただけでは、覚えられやしない。彼らの場合、歌詞も皮肉や引用に満ちているので、英語のネイティブでないと何に対して歌っているのか、すぐには判りません。大変やっかいなバンドであります。けれども一方で好きになってしまうと全部の作品を持ちたくなる、という個性的なバンドなのです。
タイトル曲の「インタビュー」は、おそらく彼らの自己紹介です。実際にメディアからインタビューを受けたときの応答をそのまま曲にしています。明白なことを何故わざわざ聞くんだ?作品を聞いていればわかるはずだろう。4作め以降で自分たちの道が定まったんだ…と曲は続きます。アルバム中で最も好きな曲がTiming。硬質なハモンドがリードし、バイオリンやディストーション・ギターが随所に入ってきます。こんな曲、世界中のどのバンドが書けるというのでしょう。ジェントル・ジャイアント風ハードロックとも言えます。
ケリー・ミネアの作曲能力、メンバーの技量もすごいですが、最もクセになってしまうのがジョン・ウェザーズのドラムズ。ベタンドタンというリズムの取り方は賑やかでユーモラスでいて、わたしはリトル・フィートのリッチー・ヘイワード並みに好きです。

Whales: The Gentle Giants (Step into Reading)
Step into ReadingシリーズのStep 3
語数 941 YL 1.2
船で海に出て、島だと思って降り立ったら、クジラの背中だった等
の伝説(シンドバッド等)もあり、昔から海の大きな生物として語
り継がれているクジラ。本書は、そんな海の生物として圧倒的な存
在感を誇るクジラについて幅広くまとめられた英語生物読本です。
本書で扱われている内容としては、クジラの種類に始まり、クジ
ラの大きさや呼吸の仕方、クジラの赤ちゃんを他の魚から守る方法
や知恵、海水温度(季節)に応じた移動、クジラが食べるもの、
音を使ったコミュニケーション、クジラの油を狙いとした捕鯨、
ホエール・ウォッチング等、幅広く書かれています。
英文は1ページに2〜5文ずつ程度の分量で書かれていて、SIR
シリーズらしく、spout, baleen, strainer, blubber等の難易度の
高い単語も出てきます。しかし、これら単語もコンテクストのある
文の中で登場しますし、学校の教科書ではなかなか出会えない単語
もあるだけに勉強になります。また絵も大変綺麗で、読解内容の
理解を深めてくれます。
クジラや生物に興味がある方には特に楽しく読めると思います。
英語のみならず、クジラに関する知識も広げてくれる、大人も楽し
める自然科学系の英語読本をどうぞ。また、類書では、I Can Read
シリーズから出ている『Amazing Whales!』があります。

ガニメデの優しい巨人 (創元SF文庫)
星を継ぐものがおもしろかったので、第2作を読みました。
どんでん返しの感じは、星を継ぐものほどのことはありません。
私は、中に出てくる個々のことで、それを調べてしまったので、いわゆるSFものを読んでいるスピードではなくなってしまい、新聞小説のように数ページづつ読むようなことになりました。本の読み方としてはちょっと異例のように自分でも思いますが、途中途中で時間を取って調べたり考えながら読むのも、別のおもしろさがありました。
人間はなぜ他の生物と、Aのことで違うのか。 Bのことで違うのか。
もともと気になっていたことなので、そっちの方、自分の思念を追求することになったのが、良かったです。
そんなこんなの事情があったので、ガニメデの優しい巨人たちという作品そのものの評価を自分の中でもちゃんとやれないのですが、問題提起がストレートですし、伏線も多く、こんな仕掛けかなと先をある範囲で想定するということでは、星を継ぐものよりも、わかり易い作品ではないかと思います。
前作ではハントとダンチェッカー二人の関係が変化の時期に当たっていたこともあり、個性も描けていたと思うのですが、ガニメデの優しい巨人たちではダンチェッカーはただ生物学者さんとして説明役になっていたのが、やや残念です。
SFはどんな面を主に評価するものか知らないのですが、途中まで考えてそのまま日常生活の中で忘れていた問題を、ガニメデの優しい巨人たちは、「こうスポットライトをあてたらどうだい」と重要な問題を、何度も出してくれるという意味では、とてもおもしろく、素晴らしい本だと思いました。
生物学や医学関連も、一般向きに昔とは違った新しい知見を紹介してくれている本がたくさん出版されていると思うので、しばらくは、そうした本を読もうと思います。
巨人たちの星や内なる宇宙とかも、やがては読みたいと思います。
ところで、人間、ヒトを1つの同質の生物と思うのは間違いではないかと考えています。 疾患や感染、アレルギー、放射性物質への耐性、知性、運動の能力、頑健さ、ストレス耐性、冒険心、恐怖傾向も、実は単なる個体差や偶発的事情、発達段階の結果ではなくて、遺伝的系統の差が色濃く出ているのではないかと考えています。 有毒、自己免疫疾患(免疫異常エピソード)も、一律に基準があったり、異常者と通常人に区分するのではない、生物学的系統で検討することのような気がしています。
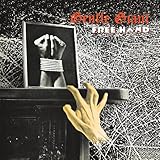
Free Hand
厳密に言えばライブを挟んで次作のIn'terviewまでは難解で複雑な構成を軸にした曲が中心になっている。
しかし、一般的に指摘されるように楽曲の充実度でみた限り、本作こそがメンタル面に於いても彼らのキャリアのピークと考えるのが妥当なところだと思う。
これまでも彼らは難解な楽曲を作り、それを難無く演奏する技術に長けているだけでなく、非常にサウンド・プロダクションに優れ、最先端のスタジオ技術を駆使して時代を超越した驚異的な音を創造してきた。
そういう実験性や進歩的な意味でのプログレッシブさこそが彼らの本質だと解釈しているが、目指していたものの共通点は10CC→ゴドレイ&クレームだとかザッパ辺りと近いように思える。
そんな彼らの最も脂の乗り切った時期の傑作として、他のビッグネームの一連の作品に埋もれる事なくこれからも継承していって欲しいアルバムだ。

Octopus
非常に完成度の高い「オクトパス」。ジャケットのデザインは何故かタコ。
音楽の内容をうまく象徴しているキャラクターではあります。
ジェントル・ジャイアントは、数多あるロックバンドの中にあって、一際
個性のあるグループですが、4枚目の「オクトパス」に至って曲のこなれ
具合と個性のバランスが丁度良い按配になりました。
相変わらず美しいコーラスと不自然なはずの転調とメロディのつながり、
リズムはつぎはぎのはずなのに、極めて自然に構成されてしまう不思議な
世界。並みのバンドではコピーさえ覚束ない、そんなアルバム。
同時代にピンクフロイドやキングクリムゾン、YESにELP等々がひし
めいたこの時期、決して引けをとらない存在であったのだと今更にして、
思ってしまいます。






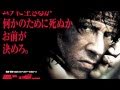
![キノコホテル<晩夏のヒメゴト>[キノコ電視台15] 鴨川つばめ](http://img.youtube.com/vi/lc0C0gydmrU/3.jpg)
